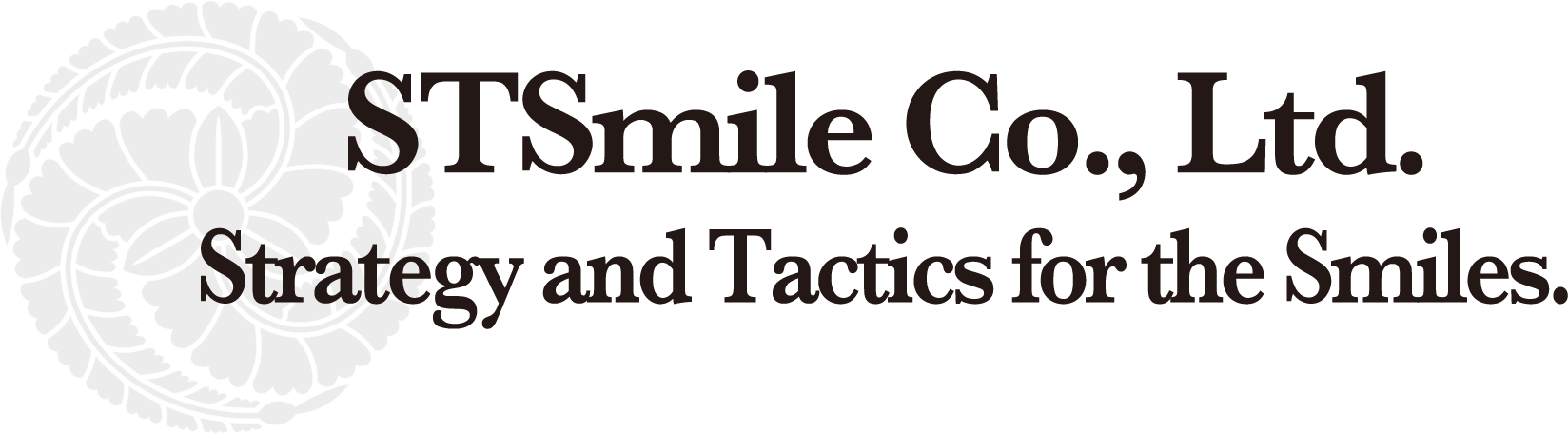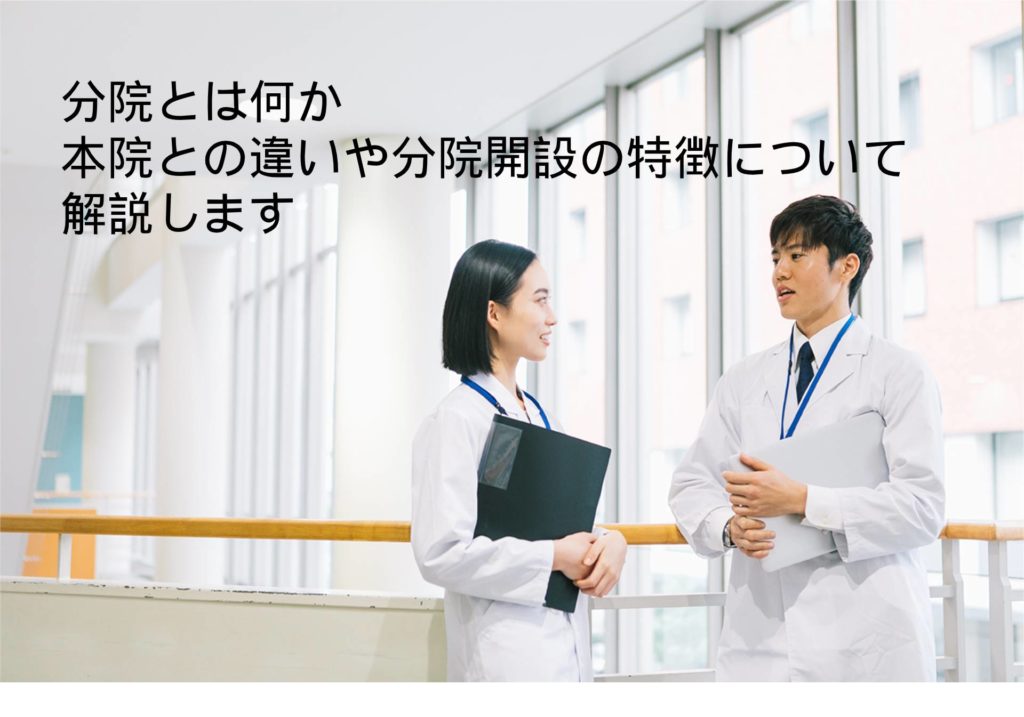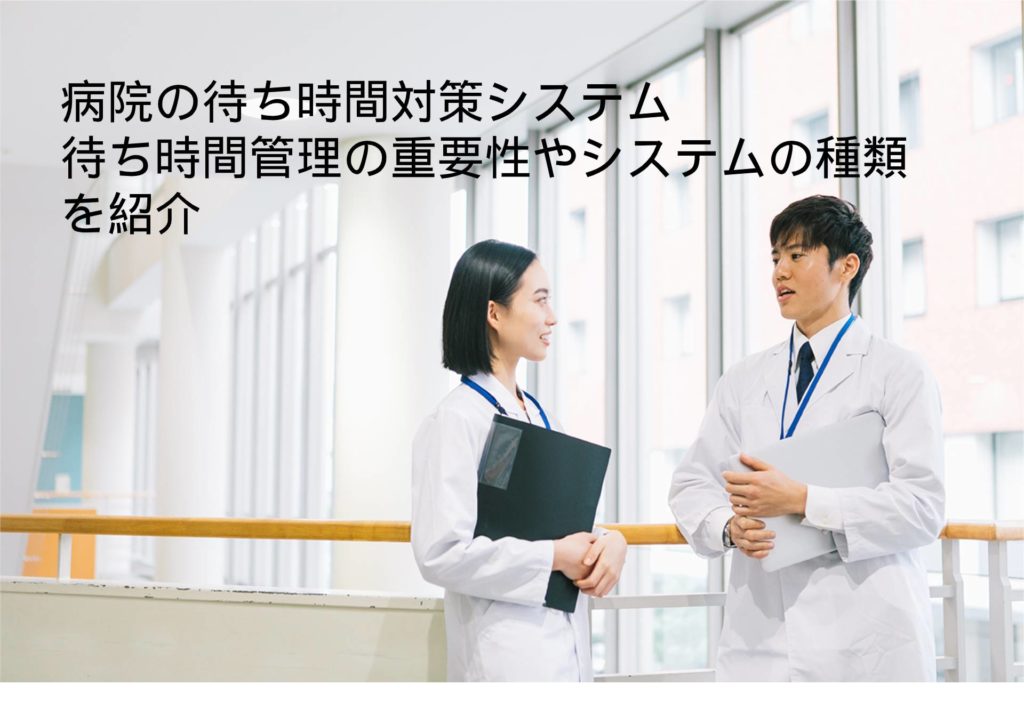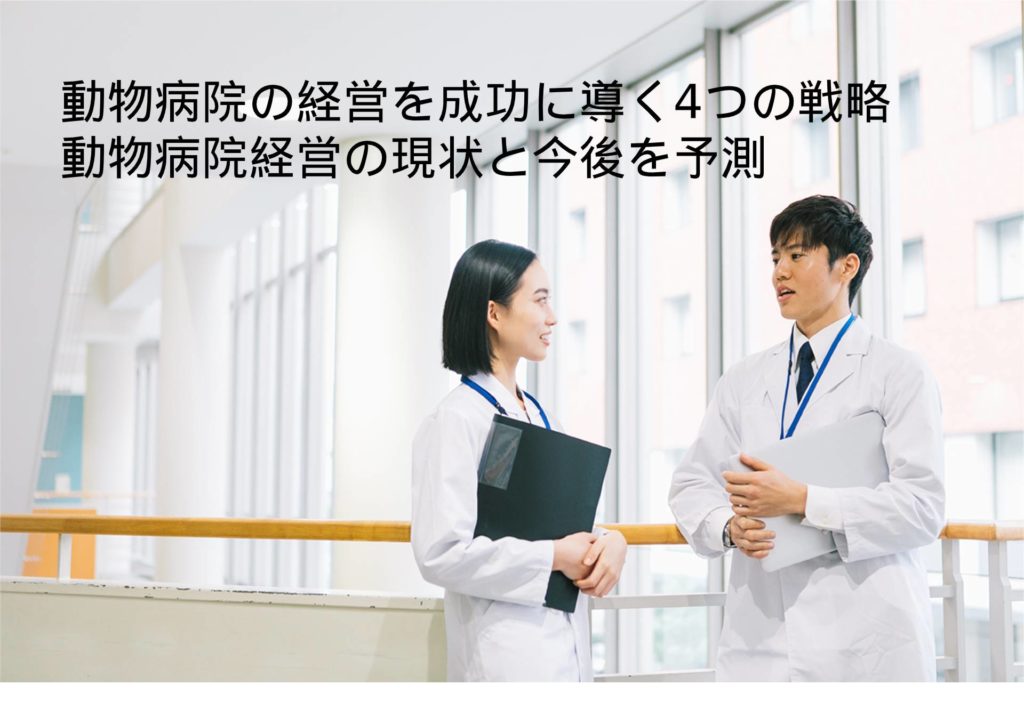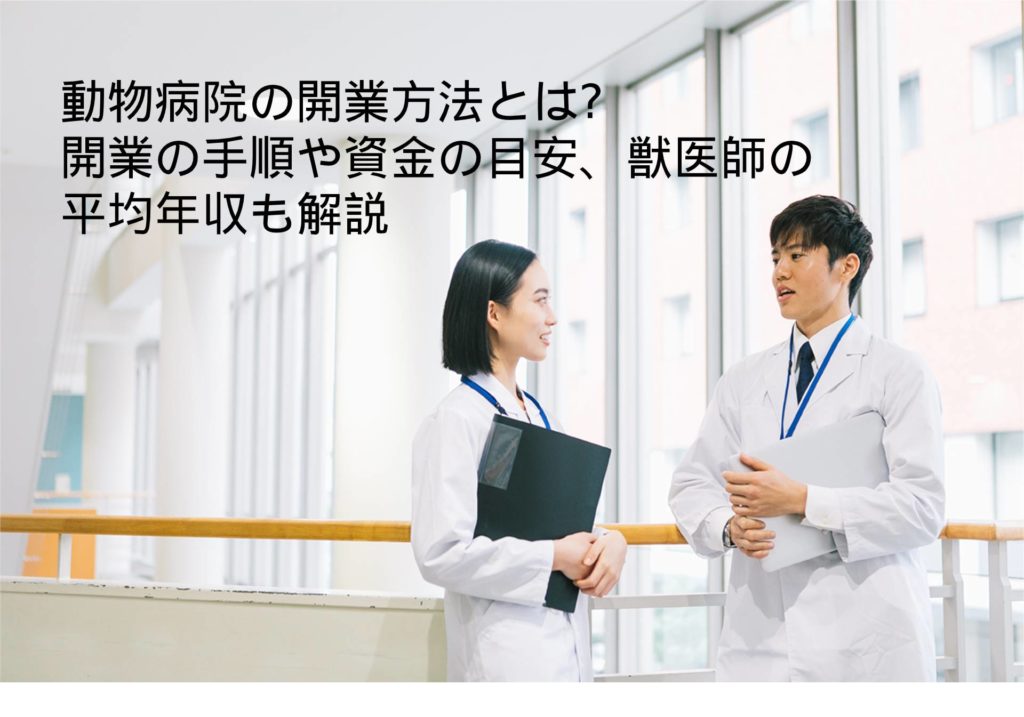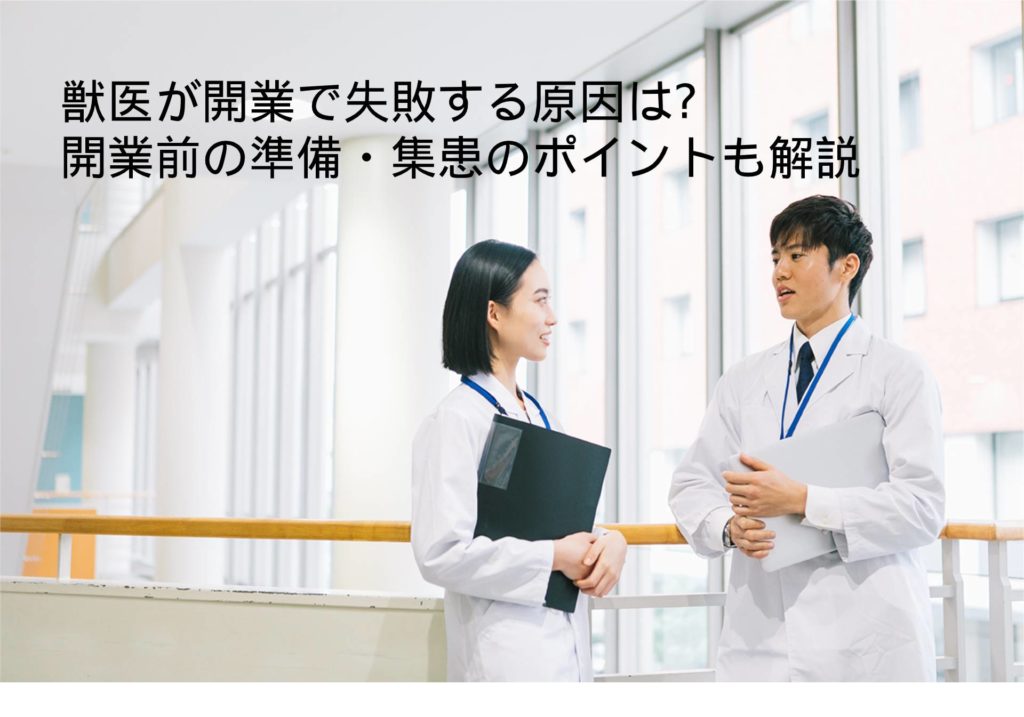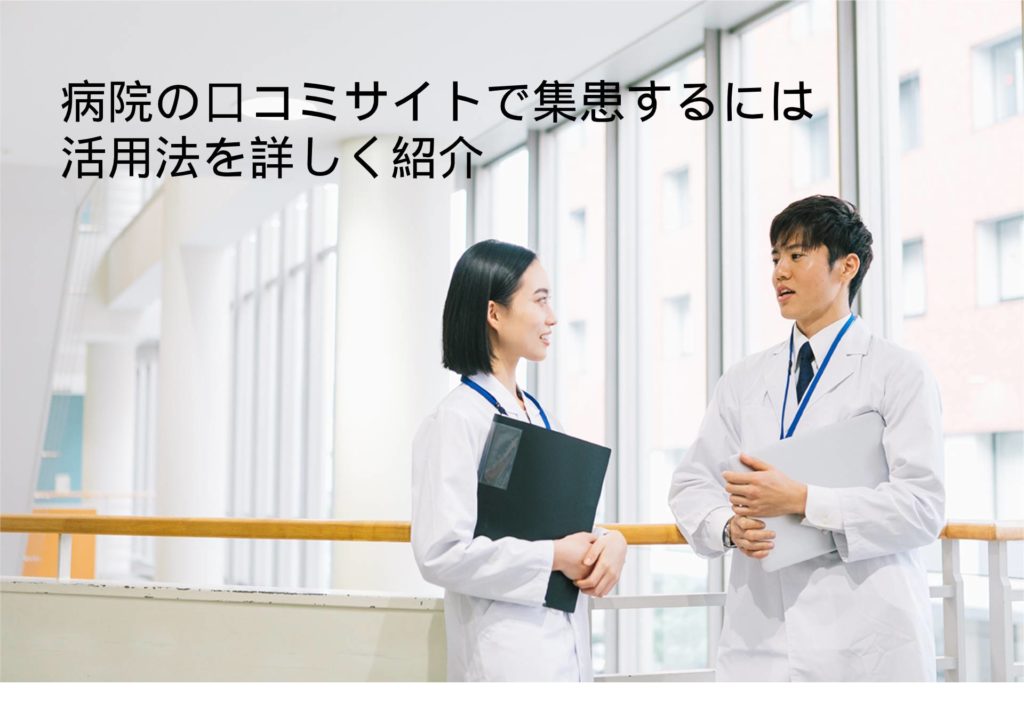医療マーケティング– category –
-

分院とは何か|本院との違いや分院開設の特徴について解説します
新たに分院を開設しようと考えていても、どのようなことに注意すべきかわからない人も多いのではないでしょうか。分院の開設は、時間や費用、労力を費やすので、失敗しないように知識を得ておくことが大切です。 この記事では、分院についての解説や、開設... -

病院の待ち時間対策システム|待ち時間管理の重要性やシステムの種類を紹介
自院の待ち時間システムの改善、あるいは開業に向けて効果的な待ち時間システムを導入しようと検討している医師もいるでしょう。 今回は、病院の待ち時間を改善するために効果的なシステムについて紹介します。システムを使った具体的な対策とともに実例に... -

動物病院の経営を成功に導く4つの戦略|動物病院経営の現状と今後を予測
動物病院を開業する際には、経営を成功に導くための戦略を立てることが重要です。この記事では、動物病院経営の現状・今後の予測・経営の戦略について解説します。動物病院経営で気をつけるべきポイントも紹介しているので、開業を検討している人は参考に... -

動物病院の開業方法とは?開業の手順や資金の目安、獣医師の平均年収も解説
動物病院を開業したいけれど、具体的にどのような手順を踏めばいいのかわからない人は多いでしょう。この記事では、開業医として独立したいと考えている獣医師の人に向けて、動物病院を開業する手順を解説します。開業のメリット・デメリット、成功のコツ... -

獣医が開業で失敗する原因は?開業前の準備・集患のポイントも解説
動物病院を開業したものの、思うように集患できずに失敗してしまうケースもあります。うまく集患できない原因は何でしょうか。集患で失敗しないためには、事前にポイントを押さえておくことが大切です。 この記事では、動物病院の開業で失敗する主な原因に... -

病院の口コミサイトで集患するには|活用法を詳しく紹介
近年では、患者がクリニックを探すときにWeb検索を利用することが一般的になっています。なかでも、患者目線の情報を得られる口コミサイトのユーザーはとても多く、集患にも大きく影響するでしょう。 この記事では、口コミサイトについての説明や、良い口...